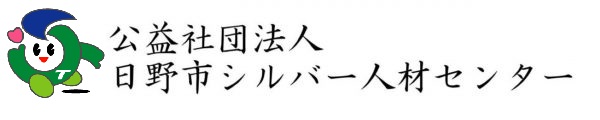会員投稿 ドーベルマン「ゼロ」 佐藤正朗
当SCの会員さんから投稿がありましたので、掲載いたします(HPのみ)。 現在「そよかぜ」には会員さんの自主的な投稿を掲載するコーナーはありませんが、今後それらの掲載方法を検討する予定です。(広報委員会)
「佐藤さん!ここでちょっと、ゼロに命令をして頂けませんか」
「えっ!私が、ですか」
するとAさんは、私にビスケットの様な餌を手渡しながら言った。
「ステイ、ヒアー(stay here)(ここに座りなさい)と、ゼロに命令してみてください」
夏の夕方、私は日野市にある駒形公園のドックランの管理小屋で18時閉門の準備に追われていた。すると見慣れたAさんが、珍しく私に声をかけて来た。
「ご苦労様です。ちょっとよろしいですか」
この方は年齢50歳位で、見れば優しそうな顔つきとは逆に体つきは筋骨隆々として逞しく、顔からは汗が噴き出ていた。どうやら愛犬ドーベルマンと―緒に散歩を兼ねて浅川を走って来たらしい。この方は、いつも私の姿を見かけると必ず「ご苦労様です」と声をかけて来るのだ。私はその度に「有難う御座います」と返事をしながら頭を下げている。だがこの日は、珍しくドーベルマンを横に従えながら私に質問を浴びせ始めた。そして首から掛けている私の名札を確認しながら喋り始めたのだ。
「佐藤さんは、お幾つになられました?」
「いや!もう81歳の爺ですよ」
「御歳にも拘らずお元気ですね。ドックランのフィールド内をいつもきれいに清掃されている姿を、私は通るたびにずっと見続けて来ました。偉いですね」
私は、そこまで褒められると少々照れ臭くなり小声で答える。
「いや、お褒めに預かり恐縮です」と言いながら再び頭を下げた。そして私からもこの方に質問をし始めた。
「このドーベルマンは何歳になりましたか?」
「6歳ですよ。人間で言えば60歳位の年齢です」
「犬の名前は、何と呼んでいるのですか」
「『ゼロ』と名付けています」 「以前は、確か奥様が毎朝9時の開門と同時に大型犬のフィールドに一番乗りをされて、この犬を遊ばせていました。その時は、確か2歳と仰っていましたから早4年の年月が経過したのですね。私は奥様が、ゼロに英語で命令しその通りに従っているこの犬の姿を目の当たりに見て驚いた記憶を、今でも鮮明に覚えています」
私は懐かしさから、自然に古い話を持ち出した。今は旦那さんであるAさんが自分の運動を兼ねて浅川の土手をゼロと一緒に走り回っていると言う。ゼロは筋肉質の体型で、眼光は鋭い。そして今では体調は1メートルを超す大型犬に成長していた。外見から見れば、今にも噛みつきそうな怖い表情が特徴である。しかし旦那さんは、何故かゼロを大型犬のフィールドでは遊ばせようとはしない。ドーベルマンと言う犬は、ドイツ原産で警察犬にも採用される程利口な犬である。Aさんは、どうやら警戒心が強く、時には主人を守るために攻撃的な性格を持ち合わせているこの犬の気性を十分知り尽くしている様である。
ふと気が付けば、私は知らず知らずのうちに目の前にいるゼロの頭を撫で始めていた。ゼロは嫌がる様子を見せず、私のなすがままにされ嬉しそうである。その姿を見て、Aさんはこう漏らしたのである。
「ゼロは、以前から知っている佐藤さんを信頼しているのですよ」
「そうですか。嬉しいですね」。どうやらゼロは、4年前に奥様と親しそうに話している私を覚えていたに違いない。
そこで私は、Aさんの言われる通りに「ステイ、ヒアー」とゼロに聞こえるように問いかけをしてみた。すると何とゼロはAさんの手を離れ、私の横に来て座ったではないか。
「いや一、驚いた。私の命令をちゃんと聞き入れてくれたのですね。しかも4年前と同じ英語をきちんと理解しているじゃないですか」
「佐藤さん、ゼロに私が渡した餌を与えてやって下さい」
言われた通りに餌を与えると、私の手にゼロの濡れた口と生暖かい感触が伝わってきた。しかし私に対して噛みつくような気配は、全く無い。
「ゼロは、いつも私や女房の命令には忠実に従いますが、それ以外の人の命令には従わない犬ですよ。「佐藤さんを信頼しきっている証拠ですね」
そして更に付け加える。
「佐藤さん、ゼロの耳を見てください。この短い耳は普段は後方に垂れていますが、今はピンと耳を立てて前方を向いているでしょう。前方に人が近付いて来るのをちゃんと見据えて警戒し、いざとなれば佐藤さんを守ろうとしているのですよ」
確かにゼロは、前方から歩いてくる入をずっと睨みつけたままで、その人から目を逸らそうとはしない。
「いや一、Aさん賢い犬ですね。私は改めて感動しました」
「佐藤さん、もう一つゼロに命令してみてくれませんか。ゼロに、『テイクリール』(take reel)(リールを取りなさい)と言って下さい」。と言いながらAさんは、手に持っていたゼロのリールを手放した。
私は、言われた通りに英語で「テイク・リール」とゼロに命令をした。
すると何とゼロは、外されたリールを口に咥えるとそのリールを私に渡そうとするではないか。私は驚くしかない。
この時のゼロと飼い主である旦那さんとの交流は、ほんの細やかな交流の一時でしかない。しかし私にとっては、心温まる楽しい瞬間であった。コロナの影響で閉ざされていた人との交流の大切さを改めて実感させられたからだ。
人生は不可思議なものに溢れている。だから私は、これからも今日の様な楽しい出会いが何度も起こることを期待して疑わない。私の人生には未だ残りの時間は、たっぷりあるのだから。